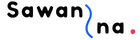飲食店のゴミ削減、まず何から始める?手軽に始められる最適解とは

顧客に食事を提供する飲食店では業種の性質上、多くのゴミが発生します。飲食店で発生した事業用のゴミは一般ごみと比較し処分に高いコストを要するため、長期的に考えるとゴミ処理の費用は無視できるものではありません。また、近年はSDGsの観点からも、店内で発生するゴミを削減することが社会から要請されています。
本記事では、飲食店でのゴミの削減について、まずはどのような種類のゴミが発生するのかを解説した後、解決策や注意点なども解説します。
店舗のゴミ処理に課題をお持ちのご担当者様、ランニングコストを下げたいご担当者様はぜひご覧ください。
飲食店でのゴミ削減の施策には手をかざすだけでおしぼりが出てくるSAWANNAがおすすめです。詳細に興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
飲食店でゴミを削減するメリット3つ

飲食店の経営において、ゴミの削減は様々な形でメリットがあります。中でも特に大きい利点について3点、理由も踏まえて具体的に解説します。
廃棄コストの軽減
飲食店から出る事業系のゴミの処理には一定のコストがかかります。実際にかかる料金は発生するゴミの量や処理業者の単価、持ち込みか回収かの形式によっても異なりますが、小規模な飲食店でも月に3万〜4万以上の料金がかかるケースも多いです。
材料費、人件費、水道光熱費に賃貸物件の場合は賃料などランニングコストがかかりがちな飲食店において、月数万円のゴミ処理コストは小さな負担ではなく、廃棄コストの軽減は経営改善に寄与します。
ゴミの処理にかかる人件費の削減
ゴミの発生に伴う直接的なコストはゴミ処理の費用ですが、間接的に発生している人件費も無視できません。発生したゴミを仕分ける、捨てるといった作業やゴミをまとめる、ゴミ置き場に運ぶといった時間に対して発生している人的コストも長期的には大きなコストとなってしまうのです。
飲食店でゴミの発生をゼロにすることは多くの業態では現実的ではありませんが、ゴミを減らすことによりその処理の工程に要する人件費も削減することができます。
SDGsへの貢献
近年は社会全体からの要請としてSDGsへの取り組みが求められます。飲食店においても例外ではなく、積極的なSDGsへの取り組みはイメージアップにもつながるのです。コストを削減しつつ、イメージ戦略としても対外的に伝わりやすい形で取り組みをアピールすることが有効といえるでしょう。
飲食店でよく出るゴミの種類

飲食店では調理場、ホール、もしくはテイクアウトやフードデリバリーなど様々な場面でゴミが発生します。具体的にどのようなゴミが発生するのか、シーンごとに見ていきましょう。
食品残渣(ざんさ)
食品残渣とは、食品由来のゴミ全般のことを指します。飲食店における食品残渣の種類や発生する場面は以下の通りです。
調理残渣
調理の過程で発生する食材の切れ端や葉や種、皮や骨などのゴミが「調理残渣」です。どのような調理残渣がどの程度発生するかは業態や提供メニューによって大きく異なります。
廃食油
揚げ物や調理の工程で生じ、廃棄する「廃食油」も食品残渣の一つです。廃食油の廃棄フローは他のゴミとは異なるため、オペレーションの面からも人件費の逼迫にもつながりかねません。
食べ残し
多くの業態の飲食店で避けられない食品残渣が、顧客による食べ残しです。店舗側でコントロールが難しい部分ですが、ビュッフェスタイルで提供している場合、手のついていない大皿の残りは近隣でニーズのある顧客に割安で販売することも考えられます。
廃棄食材
食材として利用することなく消費期限を過ぎて廃棄せざるをえなくなった食材(廃棄食材)も典型的な食品残渣の一つ。仕入れにコストがかかり、活用して利益を出すことなくゴミとしても廃棄費用がかかる廃棄食材の発生は、経営上可能な限り減らすのが理想です。
食材を無意味に廃棄してしまうことはSDGsの観点からも好ましくありません。
客席での使い捨てゴミ(おしぼり、紙ナプキン、紙の容器など)
客席で出る使い捨てのおしぼりや手・口を拭く紙ナプキン、紙の容器・トレーや使い捨てのカトラリーなども飲食店で発生するゴミの中で一定の割合を占めます。
どのようなゴミがどの程度発生するかは業態によっても大きく異なりますが、ゴミの発生を極力抑えつつ顧客の利便性も損なわない工夫が求められます。
テイクアウト・配達で出るゴミ
テイクアウトや配達などのサービスを提供する場合、その多くに使い捨ての容器やカトラリーが用いられます。こういったサービスに用いられたゴミは顧客側で廃棄するため、店の廃棄コストにはなりません。しかし、SDGsの観点から考えるとテイクアウトや配達のサービスを提供するたびにゴミを発生させている点は意識する必要があります。
すぐに実行できるゴミの削減施策

飲食店では様々な形で様々な種類のゴミが出るため、ゴミを減らすアプローチにも複数の方向性があります。その中でもすぐに取り組める施策の例について、どのようなゴミを減らせるのかも含めて見ていきましょう。
仕入れや在庫管理の見直し
廃棄食材は仕入れ・廃棄で二重に無駄なコストが発生し、SDGsの面からも好ましくありません。廃棄食材を減らす上で重要なのが仕入れや在庫管理を見直し、適切な在庫コントロールを行うこと。そのための来客予想、売上予想を立てることは経営全体にプラスに作用しえます。
メニューの再考案
食品残渣や廃棄食材を減らす上で、提供メニューを再考することも一つの有力な選択肢です。例えば、消費期限の短い食材を使うメニューを減らすことで廃棄食材が発生するリスクを下げることができます。
また、調理工程の工夫によって、調理残渣・廃食油を減らすことが可能です。例えば、チェーン店の場合セントラルキッチンで調理を行い、各店舗では簡易な調理だけで提供できるようにすることで、調理ミスによる廃棄も含めて食品残渣を大幅に削減することができます。
代替製品の導入
ゴミが出ない、もしくはゴミが出る場合であっても環境負荷を下げられる代替製品を導入することも有効な施策の一つです。取り組みによっては同時にランニングコストを下げることもできるため、経営改善の観点からも有効と言えるでしょう。
ゴミを出さない例としては紙コップで提供していたものをマグカップで提供する、使い捨ての割りばしではなく洗って再利用できる箸を導入するといった取り組みが挙げられます。ゴミの環境負荷を下げる取り組みの例としては、プラスチックのストローではなく紙のストローを導入する、プラスチックの個包装のおしぼりではなく、ウェットティッシュを提供するなど、プラスチックごみを減らす(脱プラスチック)の視点が重要です。
カトラリーの有料化、返却容器の導入(テイクアウト)
テイクアウトや配達においても工夫次第でゴミを削減することが可能です。例えば割りばしやプラスチックのスプーン・フォークなどは職場や屋外で食事をする場合には必須な一方、自宅で食事をする場合は自宅にあるカトラリーでまかなうことができます。そのため、カトラリーは選択制・有料とすることで、カトラリーを不要な顧客には提供せず、ゴミの発生を減らすことができます。
もしくは、「Loop Takeout Bento」のような繰り返し使えるリユースパッケージを提供することで、継続的にテイクアウトを利用する顧客に対して発生する使い捨て容器のゴミを削減することも可能です。
「残りもの」の販売プラットフォームの活用
一度手のついた料理の食べ残しは廃棄するしかありませんが、ビュッフェの大皿に盛られた料理の残りなどは「TABETE」などのフードシェアサービスすなわち余った食材や料理を第三者に販売できるプラットフォームサービスを活用することで買い手を探すことができます。
食品の廃棄を抑えた上で、さらに収益も見込めるため二重に経済合理性の高い施策と言えるでしょう。
ゴミの削減にあたって注意すべき点

ゴミの削減は飲食店の経営において重要な課題であり、その方法は業種・業態によってさまざまなアプローチ方法があります。ただし、ポイントを抑えずに取り組みを進めると、逆効果となりかねません。
飲食店でのゴミの削減の取り組みにあたって注意すべき点を解説します。
オペレーション変更の負荷を考慮する
新たな取り組みに際して、既存のオペレーションを大幅に変更する場合、スタッフの変更前後での負荷の増減や移行期の負荷なども考慮する必要があります。
移行期・移行後の負担が大きいとサービス品質の低下や離職にもつながりかねないため、スタッフの負担も念頭に置きながら意思決定を行うことが重要です。
顧客満足度の低下を防ぐ
ゴミの削減は経営の観点からも環境への配慮からも重要ですが、過度な削減を進め顧客満足度の低下を招くのは望ましくありません。例えば、客席において紙ナプキンの提供をやめれば紙ゴミの削減につながりますが、利便性も損なうため顧客の不満にもつながりかねません。
食材ロスを減らすためには冷凍品や既製品を活用することは有効ですが、品質が重視される価格帯の店舗においては、料理の質の低下は顧客離れに直結します。
ゴミを減らす取り組みは重要ですが、顧客の大きな不満を招いてしまうと経営自体の悪化にもつながるため、顧客への価値提供とのバランスも求められるのです。
かえって環境負荷を高めないよう注意する
ゴミの削減、とりわけプラスチックごみの削減は環境への配慮からも重要ですが、一部の脱プラスチックの取り組みは却って環境負荷を高めるという指摘も専門家から出ています。
例えば、紙ストローはプラスチックのストローと代替製品となり、プラスチックごみの削減に寄与します。しかし、紙ストロー自体の製造過程で生じる二酸化炭素はむしろ環境負荷が高いとする意見があるのも事実です。
環境への配慮を意識し、特にイメージ戦略として打ち出していく場合、目に見えるゴミの削減、脱プラスチックだけでなく、広い視点で取り組みの環境負荷を考える必要があるでしょう。
関連記事:脱プラスチックって本当に必要?反対意見や取り組む意義を解説
飲食店でのゴミの削減にSAWANNAがおすすめの理由

飲食店でのゴミの削減の取り組みには手をかざすだけでおしぼりが出てくるSAWANNAがおすすめです。SAWANNAのメリットについて、ゴミ削減の効果、コスト面、ユーザー体験の3つのポイントから解説します。
おしぼりの個包装のゴミ削減に直結
SAWANNAは手をかざすだけでおしぼりが出てくるため、当然おしぼりの個包装のプラスチックを必要としません。顧客の人数分だけおしぼりの包装のゴミを削減できることは長期的に大きなコストメリットになると同時に、プラスチックゴミ削減の観点からもSDGsに貢献することができます。
導入コスト・運用コストが低い
SAWANNAは1台39,600円と安価に導入することができます。ランニングコストもおしぼりの補充程度であり、費用をかけることなく運用することが可能です。また、スタッフが客席におしぼりを配布する必要もなく、SAWANNAのおしぼりの補充にかかる作業不可も小さいため、トータルで大きなコスト削減になると言えるでしょう。
直感的に使いやすく、衛生的
「手をかざすだけでおしぼりが出てくる」仕組みは顧客目線でも直感的に使うことができます。その上、直接触れずにおしぼりが出てくるため、衛生面でも安心して利用することが可能です。
手をかざすだけでおしぼりが出てくるSAWANNAの商品詳細については商品ページもぜひ併せてご覧ください。
まとめ
飲食店のゴミの削減について、具体的に出るゴミの種類からそれぞれに対するアプローチ方法、注意すべき点まで解説しました。
ゴミの削減は経営改善の面でメリットがあるだけでなく、SDGsの観点からも重要です。企業イメージ向上にも寄与するため、ぜひ今回の内容も参考に、自社でできる施策について取り組みやすいところから初めて見てください。
飲食店でのゴミ削減の施策には手をかざすだけでおしぼりが出てくるSAWANNAがおすすめです。詳細に興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
<参考>
・飲食店におけるグリストとは?居抜き物件選びのポイントを解説!|居抜きの神様