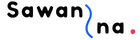ホテル業界のSDGsの取り組みとは?実践しやすい目標を事例で解説

地球温暖化などの環境の変化が日常生活にも少なからず影響を与えている現在、SDGsへの取り組みは世界中の企業、個人に求められています。食事、宿泊、入浴など様々な形で顧客のニーズに対して空間・サービスを提供するホテル業界においても例外ではありません。
しかし、一定レベルのサービス品質を要求されるホテル業界において、サービスと両立しながらのSDGsの実践に課題をお持ちのケースも多いのではないでしょうか。結論としては、ホテルが取り組めるSDGsには様々な形があり、中には低コストですぐに導入できるものや、長期的に利益をもたらすものもあり、自社に最適なものを取捨選択しながら取り組むことが重要です。
本記事ではホテルが着手しやすいSDGsの取り組みについて、具体的に実現しやすい目標も掲げつつ、具体例を出し、解説していきます。
自社でのSDGsの取り組みに課題をお持ちの方はぜひご一読ください。
ホテルでのSDGsの取り組みの第一歩としては、手をかざすだけでウェットテッシュが出てくるSAWANNAがおすすめです。興味のある方はぜひお問い合わせください。
目次
ホテルがSDGsに取り組むべき理由

企業のSDGsへの取り組みは世界全体から求められており、この要請を無視することはできません。しかし、SDGsへの取り組みは地球全体のために企業が一方的に負担を強いられるものではなく、むしろ短期的にも長期的にも利益に繋がりうるものです。
ホテルがSDGsの取り組みに力を入れるべき、自社のメリットについて解説します。
ブランドイメージの向上に繋がる
世界全体からの要請であるSDGsへの取り組みを積極的に行うことは企業のブランドイメージ向上に直結します。特に、先進的・革新的な取り組みについては世間からの注目を浴びることもあるでしょう。
SDGsへの取り組みによりブランドイメージが向上すると、ESG投資を受けやすくなったり、SDGsの推進企業とのビジネス機会増加したりといった効果も期待できます。
集客の要素となる
SDGsへの取り組みは、効果的にアピールできると集客の要素としても活用できます。国内外のSDGsへの意識の高い見込み客にとっては、取り組みそのものがホテル選びの重要な要素となりうるためです。
環境負荷のかかるサービスを簡素化する代わりに、割引やポイント付与を行うようなエコプランの提供も注目されやすいでしょう。もしくは、地域の観光施設と提携し、エコプランでの宿泊の提供も含めたエコツーリズムのパッケージ提供も競合と差別化をはかる要素となり得ます。
長期的な利益への貢献
SDGsへの取り組みは企業が利益を削って取り組む義務とも認識されがちですが、実際には長期的には様々な形で利益に貢献する可能性もあります。
例えば、プラスチックゴミやフードロスを減らす施策は即効性高く廃棄コストの削減が可能です。エコシステムの導入には初期投資を要しますが、長期的には水道光熱費の削減に繋がります。
また、将来的に法規制が強くなり、削減目標の未達に罰則が課される可能性も考えられます。そのような罰則を回避できる可能性を高める意味でも、長い目で見て今から取り組んでおく経済的メリットは十分にあると言えるでしょう。
ホテルで実践しやすいSDGsの目標

SDGsは「環境対策」と認識されることもありますが、実際には持続可能な開発に向けて「17の目標」が広く掲げられています。17の目標の中でも、ホテルの運営において実践しやすい項目について、取り組みの事例とともに見ていきましょう。
2. 飢餓をゼロに
日本では飢餓について意識する機会は少ないですが、世界には飢餓に苦しむ国もあります。食物の生産量、供給量に限りがある中「大量仕入れ、大量廃棄」の消費スタイルで食物が廃棄されることは、世界のどこかでの飢餓を促進してしまうのです。
また、現在の日本には食料が有り余っていますが、食糧自給率の低さを考えると長期的には世界情勢の変化で食料入手が困難になることもありえます。
そのような可能性まで考慮しても、ホテルでの食事の提供においても食材や料理の廃棄を極力減らすことはSDGsの取り組みと言えるでしょう。
6. 安全な水とトイレを世界中に
上下水道が整備されている日本では蛇口をひねれば安全な水が得られ、清潔なトイレを使うことができます。しかし、世界を見渡すとそうでない地域も多く存在します。世界中に安全な水・トイレを供給するにあたり、日本から貢献できるのは限りある水資源を過剰に消費しないことです。
ホテル運営においても必要以上の水の使用を控えること、浄化システムを活用して上手く水を再利用することが目標の実現に直結します。
7.エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
化石燃料の使用は発電の過程で二酸化炭素を生み出し、地球温暖化を促進します。加えて、化石燃料の総量には上限があり、永続的に使い続けられるわけではありません。
持続可能な開発を続けるためにはエネルギーの消費を極力抑えることに加え、環境負荷が低く、長期的に使用し続けられる再生可能エネルギーの導入などが求められます。
ホテルの運営にあたって、省エネシステムや再生可能エネルギーを活用することが目標実現につながると言えるでしょう。
8. 働きがいも 経済成長も
持続的な社会の発展には持続的な企業の発展も欠かせません。そのためには、従業員に働きがいをもって働いてもらいながら、顧客に価値提供を行い、経済成長していく必要があるのです。
ホテル業界は全産業の平均と比較し、離職率がやや高く人手不足になりがちな業種。従業員満足度も追求し、その上で利益をあげていく姿勢が欠かせないと言えるでしょう。
9. 産業と技術革新の基盤をつくろう
新たな技術を積極的に導入していくことも、目標の中に打ち出されています。技術革新は経営の効率化や環境への配慮など様々な恩恵をもたらす可能性があり、持続可能な経済成長に欠かせない要素なのです。
ホテルは人や空間ありきの業種ではありますが、ITやAIを活用し経営を効率化する余地もあります。最新の技術を用いることは経営効率化とともにSDGsの目標実現にも繋がりうるのです。
12.つくる責任、つかう責任
従来の「大量生産、大量消費、大量廃棄」の構造を脱却することも、持続可能な社会の構築には欠かせません。「つかう責任」においては過度に物を消費・廃棄しないことが重要です。
ホテルにおいても、使い捨てのアメニティや食事を提供する場合は食材・料理の廃棄を減らすよう取り組むなど、必要以上のごみを出さないよう努力することが求められます。
13.気候変動に具体的な対策を
気候変動、すなわち地球温暖化への対策として、CO2の排出量を削減することが求められます。エネルギーの使用を必要以上に行わないような対策に加え、必要以上にごみを出さないことも製造時や廃棄時に発生するCO2の削減に繋がります。
ホテル運営においては、エネルギーの削減やごみの発生を減らすような施策が有効です。
14.海の豊かさを守ろう
地球温暖化による気温の変化のみならず、プラスチックごみは海洋生物に直接的な影響を与えかねません。漁業による魚の乱獲も将来的な資源の減少に直結します。このような、直接的、間接的に生態系に悪影響を及ぼす原因を避けることが海洋資源の保護に直結するのです。
ホテルができる取り組みとしては、プラスチックごみの発生を減らす(脱プラスチック)に加え、MSC認証やASC認証の水産物を仕入れ、密漁者に利益を落とさないことなどが挙げられます。
ホテルでの取り組み事例

SDGsの目標達成に向けて、ホテル運営の中で取り組める施策には様々な形があります。すぐに取り組めるような施策から、長期的に大きなリターンが期待できる施策まで、具体的な事例について見ていきましょう。
食品ロス削減
食事を提供する場合、その過程の中で食材や提供した料理の廃棄を減らすことはSDGsの取り組みに直結します。SDGsへの貢献だけでなく、過剰な仕入れや大量の廃棄を抑えることは不要な食材の購入代金や廃棄コストを削減し、利益改善にも直結するのです。
例えば、ビュッフェ形式での食事の提供は需要の予測が比較的容易であるほか、調理の工夫などによって在庫のコントロールもできます。適正なオペレーションができれば仕入れがしやすいと言えるでしょう。
また、余った料理を都度販売できるマッチングプラットフォームも登場しています。
効率的なビュッフェの運営のポイントについては関連記事もご参照ください。
◆バイキング・ビュッフェの運営効率化の鍵は?導入事例つきで解説
地産地消の食材を活用
地元の食材を積極的に活用した食事の提供もSGDsの取り組みと評価できます。地産地消の食材は輸送などのリードタイムが短縮できるため、消費期限が長く食材ロスの削減に直結。さらに、輸送における燃料費を削減できることも、エネルギーの節約に貢献します。
地産地消食材の活用は地域への経済貢献にもなり、共存共栄を目指せるほか、宿泊客に対しては地元食材を使った料理の提供は集客要素としても活用が可能です。
タオル・シーツの交換頻度をゲストに選択させる
宿泊客が連泊する場合、タオルやシーツの交換や清掃を必ずしも毎日は必要としないかもしれません。
「2泊であればタオルは乾かして使うから交換不要」
「期間中、タオルは毎日換えてほしいがシーツは交換不要」
など、顧客の需要やスタンスによって必要なサービスを調節することは、清掃・洗濯に要する水道光熱費の削減のみならず、人件費の節約にも繋がります。
昨今では、SDGsの意識の高い顧客向けに、サービスを簡素化する代わりに料金を割り引いたり、追加ポイントを付与したりといった「エコプラン」の提供も有効な施策と言えます。
省エネ設備・システムの導入(LED照明、空調や照明の自動制御システム)
空調や照明の使用を控えることはエネルギーの節約に直結します。しかし、快適な温度、適切な照度の空間を提供することは顧客満足度に関わるため、過度の制限も現実的ではありません。
そこで対策となりうるのがLED照明のような省エネ設備や、必要に応じて空調・照明を自動で制御するシステムの導入。快適な環境を維持した上で、必要以上の電力消費を抑え、CO2の排出量削減に貢献することができます。
スマートチェックインやAI活用による業務効率化
従来、必ず人員を配置して行っていた業務も、最新の技術を活用することで一部または全部を自動化することが可能です。従業員の働きやすさ、働きがいを高めることや、最新の技術の活用もSDGsの取り組みと言えます。
例えば、機械の設置によってチェックインから精算、ルームキー(カードキー)の付与までが完結すれば、フロント業務の人員削減が可能です。また、例えばビュッフェの料理の残量をAIで自動で検知し、少なくなったらキッチンにアラートを出すような仕組みを整えることで、ホールの業務が効率化できます。
アメニティの詰め替え式導入
ボディソープ・シャンプーなどのアメニティは宿泊客にとって必需品です。しかし、これらのアメニティを都度、使い切りの個包装で提供していると容器の廃棄量が膨大なものとなってしまいかねません。
そのため、使い切りではなく、詰め替え式の形で提供するなど、宿泊客には従来と同水準のサービスを提供しながらその中でプラスチックごみの発生を減らすことが重要です。
SDGsの取り組みにあたっての注意点

SDGsの取り組みは世界的に求められているのみならず、長期的には自社にも恩恵をもたらす可能性が高いです。しかし、無計画に取り組んでしまうと経営の悪化に直結しかねません。ホテルでのSDGsの取り組みにあたっての注意点を解説します。
費用対効果の算出
新しい取り組みを始めるにあたって費用が発生することは少なくありませんが、費用対効果を算出することが重要です。企業姿勢としてコストをかけてSDGsに考慮した施策を行うことは評価されやすいですが、過剰なコストをかけたり過度に利益を削ったりする取り組みは経営に悪影響を出しかねません。
持続可能な開発を目指すにあたっては、取り組みも長期的に持続可能でなければならないのです。
顧客の利便性の考慮
取り組みにあたり、過度に顧客の利便性を損なってしまうとリピート率の低下を招き、売上悪化に直結しかねません。
SDGsへの配慮は現在は顧客の理解を得やすく、エコツーリズムにおいては好評価される場合もあります。例えば、過度なアメニティの提供を抑えることは環境への考慮において重要であり、顧客の理解を得やすい施策です。しかし、歯ブラシなどの必需品を有料化するのは、歯ブラシを持ち歩いていない顧客にとって実質的な値上げを意味します。
過度に顧客に負担を強いたり、不便に感じさせたりしてしまうと、満足度に大きく影響してしまうのです。
従業員の負担の考慮
SDGsへの取り組みはオペレーションの変化をもたらし、特に過渡期には従業員の負担は増します。この負担が過剰になってしまうと、従業員満足度の低下、ひいては離職を引き起こしかねません。そのため、取り組みの実施にあたっては、従業員への負担を考慮することや、事前に取り組みの趣旨や意義について説明し、理解を得ることが必要です。
SDGsの目標の中には「8.働きがいも 経済成長も」も含まれています。従業員がやりがいを持ち、組織への帰属意識を持ちながら働ける環境づくりも、またSDGsの施策として重要なのです。
ホテルでSDGsの取り組みにSAWANNAがおすすめの理由

手をかざすだけでウェットテッシュが出てくるSAWANNAは低コストで始められ、応用の幅も広いため、ホテルでのSDGsの取り組みとして非常におすすめです。世間の関心の高い脱プラスチックの施策として効果的なだけでなく、他のSDGsの目標達成にも貢献します。
SAWANNAがSDGsの取り組みとしておすすめである点について見ていきましょう。
ホテルでの実際の活用シーンについてはこちらの動画もご参照ください。
導入コストが低い
SAWANNAは1台39,600円で導入できます。大規模な設備の改修やシステムの導入などと比較し、低コストで取り入れることが可能です。導入開始にあたっても、軽量の本機を必要な場所に設置するだけなので、工事なども必要としません。
大きな初期投資を必要とせずに導入できることも大きなメリットです。
運用負荷が低い
SAWANNAは運用するにあたっても大きなコストはかかりません。基本的に必要なのは使い捨てロールの補充のみ。ロール1本あたりコストも低く(ウェットロール6本3,960円~、ドライロール12本6,600円~)、利用場所・用途にもよりますが、頻繁な補充を必要としないため、点検や補充にも大きな人手はかかりません。
ランニングコストを抑え、手間もかけずに運用し続けることができます。
顧客にも価値が分かりやすい
SAWANNAが提供する価値は非常にシンプルであるため顧客目線でも使いやすく、価値がわかりやすいこともメリットといえます。
物理的に接触することなくウェットティッシュが出てくるため、衛生面で安心であることは誰にでも伝わるでしょう。加えて、環境配慮への意識の高い顧客であればSAWANNAがSDGsの観点からも優れていることは容易に理解が得られます。
脱プラスチックをはじめとする環境への取り組みに加え、革新的な技術で新たな顧客体験を提供していることも高評価の対象なのです。
イメージを損なわない
SAWANNAは小型でシンプルかつスタイリッシュなデザインです。カラー展開もブラック、ホワイトに加えカスタムカラーも対応しているため、どのような空間に置いても雰囲気を損なうことはありません。むしろ、インテリアとしてご活用いただけます。
環境に配慮しながらも、ホテルのイメージを損なわず革新的で便利な顧客体験を提供できるSAWANNAはSDGdの取組施策として複数の観点から最適と言えます。
様々なシチュエーションで活用できる
SAWANNAは小型、軽量で持ち運びも容易なため、あらゆる場所に簡単に設置することができます。主には出入口やフロント、レストランなどでの利用が想定されますが、併設の大浴場やスポーツジム、ラウンジ、さらには各客室など、幅広く活用することが可能です。
シンプルで汎用性が高いからこそ、幅広いニーズに対応できることも魅力の一つと言えるでしょう。
まとめ
ホテルで取り組めるSDGsの施策について、親和性の高い目標について触れながら具体例とともに解説しました。SDGsへの取り組みは世界全体からの要請であり、無視することはできません。
しかし、具体的な取り組み方については様々な形があり、自社に経済的なメリットをもたらす施策も多く存在します。ブランディング、集客効果、長期目線での経済的利益など様々な形でメリットを享受できるのです。
ぜひ、今回解説した内容も参考に、取り組みやすい施策、取り組むべき施策を検討し、できることから実践してみてください。
ホテルのSDGsの取り組みの第一歩として、手をかざすだけでウェットティッシュが出てくるSAWANNAがおすすめです。
詳細を知りたい方や、具体的な活用方法について相談されたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。