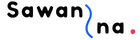ホテルの認証(グリーンキー・サクラクオリティグリーン)の取得方法を徹底解説

グリーンキーおよびサクラクオリティグリーンの認証を取得することはSDGsへの取り組みを対外的に示しやすいなど、ホテルにとって大きなメリットがあります。しかし、認証の取得ハードルは決して低くはなく、計画的な取り組みが欠かせません。
本記事では「グリーンキー」「サクラクオリティグリーン」の認証取得方法に向けて、共通する部分、それぞれの特徴的な部分に分けて徹底解説します。また、認証取得にあたっての注意点も合わせて重要なポイントを挙げています。
認証の取得を検討している、とりわけ認証の取得に向けて具体的なアクションをこれから取るご担当者様はぜひご覧ください。
手をかざすだけでウェットティッシュが出てくるSAWANNAはホテルでの認証取得にも貢献します。実際に認証を取得された企業様への導入事例もありますので、興味がある方はぜひこちらのページから詳細をご覧ください。
目次
グリーンキー・サクラクオリティグリーンとは?概要と違いを簡潔に整理

まず、認証の具体的な取得方法を解説する前に、グリーンキー、サクラクオリティグリーン双方の概要や相違点、どちらの認証をどのような企業が取得すべきかといった基本事項を解説します。いずれの認証取得を目指すか迷われている場合はぜひ参考にしてみてください。
2つの認証制度の概要
グリーンキーはホテルや観光施設を対象とするデンマークが発祥の国際的な認証制度です。国連環境計画(UNEP)や世界観光機関(UNWTO)と連携しながら運営され、世界60カ国以上で4,000以上の施設が認証を受けています。
一方のサクラクオリティグリーンは日本の宿泊業界が中心となって整備した国内認証制度。「安全」「安心」「清潔」といった日本のおもてなし文化を基軸にした品質基準を可視化する「サクラクオリティ認証」の中でも環境分野に特化した認証で、2022年から本格運用が始まりました。
対象・評価項目・運用体制の違い
グリーンキーは国際NGOであるFEE(Foundation for Environmental Education)が主導し、日本国内ではJARTA(日本ラグジュアリー観光協会)が窓口を担っています。審査にあたっては世界共通の評価基準が適用され、環境負荷の削減を最優先とした科学的・技術的なアプローチが重視されます。
対してサクラクオリティグリーンは、一般社団法人サクラクオリティマネジメント機構が主催し、自治体や観光団体との連携を重視しています。審査では「環境配慮」と「宿泊品質」のバランスを重視しており、評価項目には施設の衛生管理やスタッフの接遇、文化的配慮といった要素も重要です。環境対策だけでなく、宿泊体験そのものの品質を環境視点でどう高めるか、という視点も問われ、定量性よりも実務運用上の実効性が問われる傾向にあります。
自社に合った認証はどちらか?
いずれの認証取得を目指すのが自社にとって望ましいかはターゲット顧客や成長戦略、今後の展開方針などによって異なります。
例えば、インバウンド対応を重視する場合や、国際的な評価・比較対象としての信頼性を重視する場合は国際的に知名度の高いグリーンキーの取得が奨励されます。実際のところ、日本国内でグリーンキーを取得している多くが、外資系の施設です。
一方で、国内マーケットを主軸にする場合は、国内での評価に特化したサクラクオリティグリーンの認証取得が望ましいでしょう。実際、日本国内ではサクラクオリティグリーンの認証の方が選択されている傾向にあります。認証が5等級に分かれており、特に最初の等級の取得にあたっては相対的にハードルが低いことも魅力です。
認証取得の流れと必要な準備(共通編)

2つの認証において重視されるポイントなどに違いはありますが、大まかな流れや求められる準備については共通する部分も多くあるのです。そこで、それぞれの詳細を解説する前に両者に共通するポイントについて解説します。
自己診断・現状把握
どちらの認証取得においても、まず求められるのは自社施設の現状分析を行い、認証取得の評価基準を比べてどの程度の位置にいるか把握することです。
グリーンキーの場合、公式ガイドラインに基づいた自己評価チェックリストが提供されているため、リストと照合することで、項目別のスコアを確認することができます。サクラクオリティグリーンもウェブサイト上で基準を確認できるほか、事前相談を活用することも可能です。様式に沿った申請書の提出と、個別項目に対応した証拠書類の準備が必要です。
書類・証拠提出の準備
認証の取得にあたっては、個別項目に対応した証拠書類の準備が必要です。例えば、節水設備を導入した場合、設置機器の写真、型番、マニュアル、設置工事報告書などの実際に設置されている証拠を示す必要があります。
スタッフへの教育を施策として実施した場合は研修資料や受講者名簿、実施日程といった証拠を保管するだけでなく、実際に研修を実施している写真・映像なども記録しておくとよいでしょう。
第三者評価とフィードバック対応
いずれの認証でも、書類審査の次に実施されるプロセスが現地訪問(またはオンラインでのインタビュー形式)による第三者評価です。審査員は、申請内容と現地の実態が一致しているかを多角的に検証します。衛生管理の導線、水回り設備の配置、実際の廃棄物管理状況などがチェックされ、記載と相違がある場合は追加資料の提出や是正が求められることもあります。
設備を適切に導入していても審査員からの質問に的確に回答できず、基準に合致していると納得させられなかった場合、減点対象となってしまうケースも。そのため、ロールプレイングなども含めた審査員対応の準備も怠らないようにしましょう。
取得後の継続的改善義務と更新手続き
いずれの認証も認証取得後も1年〜2年ごとの更新が必要であり、更新時には再度の審査や新たな取り組みの報告が求められます。つまり「一度基準を満たせば終わり」ではなく、「基準を維持・向上させ続ける姿勢」が評価されるのです。
更新に際して新たな審査基準が追加されることもあるため、常に最新のガイドラインに目を通し、柔軟な対応力を維持することが求められます。
グリーンキー取得の詳細プロセスとチェックポイント

グリーンキーは国際的に広く認知された環境認証であり、その取得には厳格な審査と継続的な改善姿勢が求められます。実際の申請から認証取得に至るまでの詳細なプロセスと、途中でつまずきやすいチェックポイントについて見ていきましょう。
申請~現地審査の流れ
グリーンキーの認証取得プロセスは、以下の流れで進みます。
- 事前相談と登録
まず、認証を希望する事業者はグリーンキーの窓口に登録・相談を行います。この段階で概要や審査方針の説明を受け、自施設における取得の見通しを立てます。 - 申請書類の提出
次に、公式の申請フォームに記入し、施設情報や運営方針、環境配慮に関する実践事項などをまとめて提出します。ここでは単なる記述だけでなく、各項目の証明となるエビデンスの添付が重要です。 - 書類審査・一次フィードバック
提出資料はグリーンキー日本支部の担当者により精査され、不備や不足があれば修正依頼が届きます。この段階での対応の丁寧さが、次の現地審査の通過率に大きく関わります。 - 現地審査(施設訪問)
担当審査員が実際に施設を訪問し、書類に記載された内容が現場で実践されているかを確認します。ヒアリングや視察に加え、施設運営責任者や現場従業員への質問も行われます。 - 最終判定・認証発行
書類と現地審査を経て、すべての基準を満たしていると認められた場合に、正式な認証が発行されます。
必要となる書類や証拠
グリーンキーの審査において必須とされる証拠資料には以下のようなものが含まれます。
- 清掃・洗浄マニュアルや衛生管理計画
- 節水・省エネ設備の導入証明(仕様書、写真など)
- ごみ分別やリサイクル体制の記録
- 食材調達における地産地消・オーガニックの証明
- 従業員向けの環境教育の記録や教材
施設の規模や形態によって提出すべき書類は変わりますが、「施策が計画され、運用され、記録されている」ことを証明できる資料であることが共通の要件です。
提出前に確認すべきこと
申請前に確認しておくべき重要なチェックポイントは、「書類と現場の整合性」と「日常的な実施状況」です。書類で立派な計画を記載していても、現地でその通りに運用されていなければ評価は下がります。
よって、申請前には関係部署との情報共有を徹底し、実際の業務フローや運用マニュアルが評価基準とズレていないかを再点検することが不可欠です。第三者の専門家や外部コンサルによる模擬レビューを受けるのが望ましいでしょう。
サクラクオリティグリーン取得の詳細プロセスとポイント

サクラクオリティグリーンの評価基準が5段階に分かれており、施設の環境レベルに応じたステップアップが可能です。サクラクオリティグリーン独自の申請・評価の流れや、準備すべきポイントを具体的に解説します。
1〜5等級の基準と評価ポイント
サクラクオリティグリーンでは、環境取り組みのレベルに応じて1〜5等級で認証を行っています。1等級が最も基本的な環境配慮を示すレベル、5等級が国際的に通用する高水準の取り組みを評価する最上位ランクです。
評価項目は大きく分けて以下のようなカテゴリに整理されています。
- エネルギー・水の使用効率(節電機器の導入、水栓の自動化等)
- 廃棄物管理(分別回収体制、使い捨て用品削減の工夫)
- 化学薬品の管理(環境配慮型洗剤の使用など)
- 地域社会や顧客との連携(地域食材の使用、情報開示)
- 従業員教育・ガバナンス体制
高い等級を目指すほど、これらの施策を「体系的に」「継続的に」実施しているかが重視されます。加えて、取り組みを支える経営方針やスタッフの理解度も評価対象に含まれる点が特徴です。
現地審査で重視される内容
申請書提出後には、サクラクオリティ認証機構の専門審査員による現地訪問が行われます。審査においては、記載された環境施策が日常的な業務に組み込まれているかどうか、形だけでなく「運用面での定着」が見られます。
とくに重視されやすいのが以下のポイントです。
- 従業員が自施設の環境施策を理解し、実行できているか
- マニュアルやルールが現場に落とし込まれているか
- 来館者にも分かりやすく環境配慮を伝えているか(掲示物・WEB表記など)
また、評価時には改善提案も受けられるため、将来的な等級アップを見据えた中長期的な環境施策のロードマップを示しておくことも望ましいとされています。
提出書類と写真・証拠資料の準備
申請時には、所定の申請書類に加えて、実際に行っている環境施策の「証拠資料」の提出が求められます。
- ごみ分別の様子や回収体制が分かる写真
- 客室内で使用している再利用品、環境配慮型アメニティの画像
- 従業員教育用マニュアルの抜粋
- 地産地消に関するメニューや調達方針の文書
- 使用エネルギー・水使用量の削減実績(定量的記録)
さらに、施設紹介パンフレットやホームページにおける環境対応方針の記載なども評価対象となります。つまり、社内の取り組みだけでなく「社外への発信」が整っているかも重要です。
認証取得を進めるうえでの実務上の注意点

認証の取得を進める中で、審査基準をクリアするための設備投資やオペレーションの制定を無計画に行うと、かえって減点対象となったり、業務効率全体が低下したりする懸念もあります。実務上の注意点やスムーズに準備を進めるポイントについて見ていきましょう。
現場オペレーションとの調整
認証の基準をクリアするための施設運用において、過度に現場オペレーションに負担がかかると品質の維持が困難になります。認証は一度取得して終わりではなく、品質を維持・向上させていくことが重要です。そのため、現場に大きく負担がかかり、恒久的に維持できないような運用は、長期的には認証の維持を困難にするほか、様々な弊害が発生しかねません。
現場の負担や継続的な運用が可能かも考慮しながら、基準クリアのための施策を検討していく必要があります。
従業員教育と巻き込みの重要性
環境認証は、設備だけでなく人的運用も評価対象に含めています。特にサクラクオリティグリーンでは、スタッフの理解度や意識も審査の観点です。そのため、認証取得にあたっては現場のすべてのスタッフを巻き込むことが不可欠といえるでしょう。
社内向けにわかりやすく、かつ継続的に学べる教育プログラムの整備、朝礼での共有やEラーニングの導入、ポスター掲示といった複数の手段を活用することが奨励されます。また、認証取得の意味について周知し、スタッフの帰属意識を高めることも効果的です。
外注や補助金活用も検討を
試作によってはすべての取り組みを自前で完結させるのは難しいケースも多いため、外部の専門家や支援制度をうまく活用することも重要な選択肢です。たとえば、環境コンサルタントやサステナビリティ専門家を活用すれば、現場と認証基準の間のギャップを適切に埋めるアドバイスが得られます。
また、設備の導入などにおいて多額の投資を要する場合、補助金・助成金を活用することも有効です。認証取得への取り組みはSDGsへの取り組みと直結するため、補助・助成の対象となりやすく、積極的な活用が奨励されます。地域によっては認証の取得自体に補助金が出るケースもあるため、活用できる制度の情報収集は必須です。
SAWANNAが認証取得を支援できる理由

認証の取得にあたって、一つのソリューションとして手をかざすだけでウェットティッシュが出てくるSAWANNAがおすすめです。脱プラスチックの施策として有効な他、従業員のオペレーションも逼迫せず、対外的な取り組みの訴求力もあります。
SAWANNAが認証取得の支援となる理由を見ていきましょう。
ホテルでの実際の活用シーンについてはこちらの動画も併せてご参照ください。
プラスチックごみ削減と衛生管理の両立
SAWANNAは手をかざすだけで清潔なウェットティッシュが出てきます。そのため、個包装のおしぼりや除菌シートなどに代替することによりプラスチックごみの削減に大きく貢献します。
ホテルや併設のレストランにおいて衛生管理は極めて重要ですが、SAWANNAは衛生面を担保した上で、脱プラスチックの有効な施策として活用が可能です。
現場の負担を増やさずに基準をクリア
環境認証取得における大きな障壁の一つが、「基準を満たすためのオペレーション変更」に伴う現場の負担です。現場の負担が大幅に増える施策は継続性がなく、評価されない場合もあります。
SAWANNAは置いておくだけで機能し、顧客に対して使い方の説明等も要しません。必要なオペレーションはウェットタオルの残量の点検や補充のみであり、現場に大きな負担を強いることなく運用することが可能です。導入にあたって、マニュアルの整備や教育等も要しないため、管理者、現場双方が負担なく導入を進められます。
高評価に繋がる施設運営の支援ツールとして活用可能
2つの認証は両方とも「環境に配慮した施設運営」と「ゲストへの明確な説明・発信」を重視しています。SAWANNAは、手洗いを視覚的に印象づける特徴的なデザインや非接触で衛生的、簡単に利用できる構造によって、宿泊者・利用者に強い印象を残します。施設側が「使い捨て削減」「環境対応の姿勢」を発信するツールとして最適といえるでしょう。
実際のところ2025年6月にグリーンキー認証を取得されたメルキュール札幌様でもSAWANNAを導入いただいており、認証の取得に一役買っています。
SAWANNAの製品に関するお問い合わせ、認証取得に向けた導入のご相談はお気軽にご連絡ください。
まとめ
グリーンキーおよびサクラクオリティの申請方法について、それぞれの共通する部分、特徴的な部分を解説しました。いずれの認証取得を目指す場合においても、まずは現状をしっかりと把握した上で、基準をクリアするための現実的な取り組みを策定し、しっかりと現場に落とし込むことが必須です。
ぜひ今回解説した内容も参考に、具体的な認証取得に向けたアクションプランを立て実践してみてください。
グリーンキーやサクラクオリティグリーンの認証取得には手をかざすだけでウェットティッシュが出てくるSAWANNAがおすすめです。低コストで現場に負荷をかけることもなく導入できますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。