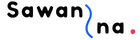「グリーンキー」「サクラクオリティグリーン」とは?認証の比較や取得メリットを解説

ホテル業界における第三者機関による認証として重要なものが「グリーンキー」および「サクラクオリティグリーン」です。両者は環境への配慮を中心としたホテルの施策を客観的に評価し認証を行うもので、認証の獲得には一定のハードルがありますが、経営において様々なメリットがもたらされます。
本記事では「グリーンキー」「サクラクオリティグリーン」の認証について、認証取得が求められる理由や、それぞれの認証の特徴、認証に必要なステップを解説します。また、運営する施設がどちらの認証を取得すべきかについての判断基準も併せて記載。
認証の取得を検討している、もしくは認証の取得に向けて具体的なアクションを策定したいご担当者様はぜひご一読ください。
手をかざすだけでウェットティッシュが出てくるSAWANNAはホテルでの認証取得にも貢献します。実際に認証を取得された企業様への導入事例もありますので、興味がある方はぜひこちらのページから詳細をご覧ください。
ホテル業界で認証取得が必要な理由

「グリーンキー」「サクラクオリティグリーン」それぞれの認証について詳細を解説する前に、まずはそもそもなぜ認証を取得すべきか解説します。SDGsへの取り組みとして有効なだけでなく、経営の視点からも重要です。
SDGs訴求の強化
SDGsへの取り組みは今や企業にとって欠かせないものとなりつつあります。特に、一般消費者を相手にするホテル業態においては具体的な取り組みを紹介するなど、対外的にわかりやすく訴求する必要性が高いと言えるでしょう。
認証を取得することで、誰の目にもわかりやすくSDGsへの取り組みを積極的に実施しているホテルであることをアピールすることが可能です。認証の取得にあたって評価された取り組みをわかりやすく打ち出すことで、さらに効果的なPRができます。
ESG投資や企業評価への好影響
ホテルや運営企業の評価向上やESG投資を狙うにあたっても認証は大きな効果をもたらします。
環境への配慮は現在、どのような企業においても評価対象となります。認証を受けることで業界の中でも特に高水準で環境への配慮を行っている企業であることを示しやすいため、高評価の対象となりやすいのです。単に企業イメージを向上させるにとどまらず、ESG投資を受けるにあたっても、プラス評価の対象となりやすいでしょう。
海外ゲストやZ世代を対象とした集客効果
認証の取得は企業イメージ向上だけでなく、直接的な利益につながる集客効果も見込めます。「認証を取得した環境へ配慮に優れたホテル」というイメージは、環境意識の高い顧客にとってホテル選びにおいて有力な選択肢となるのです。
とりわけ、海外からの旅行者やZ世代の若年層は環境問題への関心が高い傾向にあります。認証の取得はそういった層の顧客にとって、自社のホテルを選択する一つの大きな要素となるでしょう。
従業員の意識向上
従業員にとって認証の取得が働くモチベーションにもなる場合もあります。認証は高い評価基準を満たしていることを対外的に示せる証。そのため、働いているホテルが認証を取得している事実は従業員にとって帰属意識を高めることにもつながりうるのです。
そのような形でのモチベーションの向上は従業員の気を引き締めるため、業務品質の向上にもつながります。結果として顧客からの高評価のレビューを受け取れ、さらにモチベーションが高まるといった好循環にもつながるでしょう。
「グリーンキー」と「サクラクオリティグリーン」

ホテルが取得を目指すべき認証である「グリーンキー」と「サクラクオリティグリーン」について、それぞれの運営団体や評価項目などの概要を解説し、比較します。自社がどちらの認証取得を目指すべきかご参考ください。
グリーンキーは国際的に通ずる認証
グリーンキーは世界的な環境教育団体である「FEE(国際環境教育基金)」が運営する国際的な環境認証制度です。主にホテルやキャンプ場などの観光施設を対象とし、「エネルギー」「水資源」「廃棄物」「食品調達」「環境教育」など13のカテゴリ・100項目以上の基準で審査されます。
項目は義務項目と推奨項目に分かれており、段階的に持続可能な運営を目指せる点が特徴です。世界70カ国以上で導入されており、国際的な信頼性と認知度を活かしたESG対応やインバウンド施策にも有効です。
国内で広く扱われるサクラクオリティグリーン
一方のサクラクオリティグリーン(Sakura Quality An ESG Practice)は、国内の宿泊施設向けに開発された環境認証制度。日本観光振興協会などが中心となって推進しており、総合的なホテルの品質を保証する「サクラクオリティ」の中で環境への取り組みに特化した認証という位置づけです。
SDGsの17ゴールに紐づく最大172の項目で構成され、施設の環境対応や地域との共生を可視化します。評価は5段階(御衣黄1〜5)で表され、持続可能性の実践度に応じてランク付けされます。国内独自の視点から、より地域密着・実効性のある評価が可能で、日本の観光品質と調和した環境配慮を実現します。
グリーンキーとサクラクオリティグリーンの比較
グリーンキーとサクラクオリティグリーンはどちらかに優劣があるようなものではありません。そのため、自社にとってより好ましい、取得にメリットの大きい方を選択することが求められます。
国際的な認知獲得を狙う場合、国際的な認証であるグリーンキーの認証を目指すのが効果的でしょう。一方で、国内に限って言えばサクラクオリティグリーンの方が広く認知されています。そのため、国内中心、日本人相手での事業展開を考えるのであればサクラクオリティグリーンが適切な選択肢の可能性が高いと考えられます。
| 比較項目 |
グリーンキー (Green Key) |
サクラクオリティグリーン (Sakura Quality Green) |
|---|---|---|
| 運営団体 | FEE(国際環境教育基金) | 日本観光振興協会など |
| 主な対象施設 | ホテル、観光施設 | 宿泊施設(旅館・ホテルなど) |
| 国際性 | 高い(70か国以上、6000施設以上が取得) | 日本国内を中心とした認証制度 |
| 評価基準 | 13カテゴリ・100項目以上(義務項目と推奨項目) | SDGs17ゴールに紐づく最大172項目 |
| 評価の段階 | 推奨項目遵守率で段階的に強化(毎年更新・審査) | 5段階(御衣黄1~5)で評価(年次更新) |
| 審査方法 | 書類審査+現地審査 | 書類審査+現地審査(フェーズⅠとⅡ) |
| ブランド・営業効果 | 国際的な信頼性が高く、海外旅行客・ESG投資対応に有効 | 国内ブランドとして安心感を訴求、自治体補助・国内評価向上に有効 |
| SDGsとの関連性 | SDGsとの対応を明確に評価 | SDGs17の各目標に直接対応した評価設計 |
| 導入ハードル | やや高め(中長期的な改善が前提) | 柔軟性が高く、中小施設や地方施設でも導入しやすい |
認証取得の流れと必要なステップ

グリーンキーとサクラクオリティグリーンは、持続可能な観光業を目指す施設にとって有効な認証です。認証取得に必要なプロセスには共通する部分も多いですが、一部には相違点も見られます。取得に向けた流れについて、共通する部分をステップごとに整理し、それぞれの相違点や注意点を解説します。
ステップ1:準備と自己点検
最初のステップは、基準を理解し、自施設の対応状況を確認する段階です。グリーンキーではFEEが定める100以上の評価項目(13カテゴリ)に基づき、自己診断ツール(Green Key Toolboxなど)を活用してチェックを行います。一方、サクラクオリティグリーンもSDGsに基づく評価基準が設定されており、施設ごとに実行可能な項目を事前に洗い出します。
この段階で重要なのは、評価に対応できる体制を整備することです。例えば、環境責任者の配置、各部署への指導、改善計画の策定などが求められます。いずれの認証取得を目指すにあたっても「どこまでできているか」「何が不足しているか」を可視化するための準備フェーズと言えるでしょう。
ステップ2:申請と書類審査
申請の準備が整ったら、申請書を提出し、書類審査が行われます。
グリーンキーではナショナルオペレーター(日本ではJARTA)に対し、義務項目すべてへの対応状況と証拠書類を提出します。評価には環境方針、ゴミの分別指針、省エネ計画、従業員への教育内容などの文書が含まれます。
サクラクオリティグリーンでは、「品質認証(フェーズI)」の申請から始まり、SDGs実施状況の報告資料、地域連携や環境負荷低減に関する取り組み内容を文書で示す必要があります。
どちらの制度でも、日々の取り組みを客観的に示す証拠資料の質と整備状況が重要です。
ステップ3:現地審査(オンサイト審査)
書類審査の後は、施設に実際に審査員が来訪しての現地審査が行われます。
グリーンキーでは初年度に必ず現地審査が実施され、現場での衛生状態、掲示物、スタッフの理解度などが確認されます。2年目以降は隔年で現地審査が行われ、現地審査が行われない年は書類審査という運用です。
サクラクオリティグリーンでは、品質認証の後に「実地認証(フェーズII)」として現場確認が実施される他、覆面調査も実施され、より実践的な取り組みが評価されます。施設の運営方針と実態が一致しているか、改善の取り組みが日常業務に定着しているかがポイントです。
ステップ4:認証取得と活用
現地審査を通過すれば、認証が取得できます。
グリーンキーでは認証証とロゴマークが授与され、FEEの国際データベースに登録されます。これは国際的なブランディングにおいて非常に有効で、特にESG対応や海外顧客向けの信頼性向上に寄与します。
サクラクオリティグリーンでは、評価ランクに応じて「御衣黄○等級」といった形での認定がなされ、パンフレットやWebサイトでのPRに活用できます。国内の観光振興施策との連携や、地方自治体の補助対象となるケースもあるため、国内戦略との相性が良いのが特徴です。
ステップ5:継続的な改善と更新審査
どちらの制度も、一度認証を取得すればよいものではなく、その品質を維持、向上させていく必要があります。特にサクラクオリティグリーンの場合、等級を高めるためには改善が必須です。
そのために、継続的な取り組みを続け、定期的に再審査を受けることが求められます。
グリーンキーの場合、更新ごとに義務項目の遵守を維持しながらガイドライン項目の達成率を段階的に高めていくことが重要です。そうすることで年々持続可能性の水準を高めていく仕組みとなっています。
サクラクオリティグリーンでも年次での更新審査が行われ、取り組みの深化や新たな地域貢献の評価などが審査されます。ランクアップを目指す場合には、より高度な対応や実績の積み上げが必要です。
取得事例と参考になる取り組み

実際の認証の取得事例について、グリーンキー・サクラクオリティグリーン双方の事例を、実際に評価されている取り組みの一部を含めながら解説します。
ウェスティンホテル東京(グリーンキー)
ウェスティンホテル東京では館内全体で80%以上のリサイクル率を達成しています。また、AIカメラやWinnowモニターを活用して食品廃棄物の削減にも成功。このような取り組みが評価され、「廃棄物管理」で高い評価を受けています。
加えて、多くの水栓での水流制限による水資源の節約や洗剤類を環境認証済製品へ切り替えることによる化学物質の抑制、従来使用していたプラスチック容器を紙や植物由来の素材に代替するなど、総合的な施策が評価され、認証の取得に至っています。
さらに、ベジタリアン・ヴィーガンメニューの提供や地産地消食材の活用、ジェンダー平等推進や育休制度整備といった社会的取り組みも併せて推進されています。
ザ・リッツカールトン大阪(グリーンキー)
ザ・リッツ・カールトン大阪は省エネ照明への切り替えや再生可能エネルギー活用、空調・照明制御等により省エネ体制の強化に成功しました。
水資源の節約、排水管理においては節水設備や排水処理などのインフラ整備が実施されています。廃棄物削減、とりわけプラスチックの削減においては客室アメニティやレストランでの使い捨てプラ容器の撤廃と代替素材の導入により廃棄物を低減。
さらに多様な人材採用、地域イベント参画、文化発信プログラムなど「Community Footprints」に基づくCSR活動も評価されています。
メルキュール札幌(グリーンキー)
メルキュール札幌は2025年5月に北海道で初となるグリーンキー認証の事例です。LED照明への全面切替え、HVAC制御システムの導入による省エネ体制の構築に加え、定期的な環境パフォーマンスのモニタリングと目標設定による環境管理を実現しています。
ごみの計量・圧縮・分別回収実施などの廃棄物管理を実施するとともに、シングルユースプラスチックを廃止し、アメニティやテイクアウト小物を紙・木製へ切替など脱プラスチックについても積極的な取り組みを行っています。このような施策の中の一つとしてSAWANNAもご導入いただいています。
帝国ホテルグループ(サクラクオリティグリーン☆ 5)
帝国ホテルグループは国内で唯一、サクラクオリティグリーンにおいて最高ランクとなる5 御衣黄ザクラ(最大5段階)を取得しています。
脱炭素・エネルギー管理においては2030年までにCO₂排出量を2013年比で40%削減、2050年までに実質ゼロを目指すロードマップを策定。2023年10月より東京・大阪においてCO₂フリー電力を導入しています。
プラスチック削減の取り組みとして2022年に客室アメニティ等12品目のプラスチック素材を代替。2024年には対2019年比で88%のプラスチック削減に成功しました。客室で使用済み石鹸を回収・再利用し、貧困地域へ寄付するプログラムを実施するなどの取り組みも評価されています。
クロスホテルグループ(サクラクオリティグリーン☆ 4)
札幌・京都・大阪に施設をもつクロスホテルでは、上から2番目の評価である4 御衣黄ザクラを取得しています。
SDGs 17ゴールに沿ったプログラムを策定し、継続的に実施。さらに、環境配慮型の清掃や運用・サービス導入するなどのサステナブルな施設運営も高い評価を獲得。クロスホテル大阪では大阪「ミナミ」地域の歴史や地元製品を取り入れた展示・イベント開催も「地域文化・伝統の活用」として評価対象とされています。
ホテルオークラJRハウステンボス(サクラクオリティグリーン☆ 1)
長崎県のホテルとテーマパーク一体型の施設ハウステンボス内にある施設の一つ、ホテルオークラ JRハウステンボスはサクラクオリティグリーンの認証第一段階である1 御衣黄ザクラを取得しています。
安全性や衛生面について法令遵守に基づいたクリアな取り組みが確認。とりわけ顧客とスタッフ双方の健康・安心を最優先に考え、衛生管理体制の強化に重点を置いた運営体制が評価されました。
この先で環境配慮や地域連携の取り組みを重ねていくことにより、上位ランクの認証取得が可能になります。
認証取得にSAWANNAが貢献できる理由

グリーンキーやサクラクオリティグリーンなどの認証取得には手をかざすだけでウェットティッシュが出てくるSAWANNAがおすすめです。SAWANNAがどのような観点から認証取得に貢献できるのか、具体的に3つのポイントから解説します。
ホテルでの実際の活用シーンについてはこちらの動画も併せてご参照ください。
廃棄物の削減になる
SAWANNAを活用することで、個包装のおしぼりの包装部分のごみを削減することが可能です。1つのおしぼりの包装の量は数グラム程度ではありますが、1人の宿泊者が1泊に対し複数回使うことを想定すると、年間で出るゴミの総量は無視できるものではありません。
廃棄物の削減は環境負荷の軽減に直結し、認証取得の中でも評価要素の一つとなっています。
二酸化炭素削減への目標設定ができる
個包装のおしぼりのごみを減らすことは単なる廃棄物の削減にとどまらず二酸化炭素削減への具体的な目標設定につながります。
環境への取り組みの中でも、二酸化炭素削減は特に重要な施策のひとつです。二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスは地球温暖化を招き、様々な形で生態系に悪影響を与えかねません。そのため、二酸化炭素の削減は具体的な目標を設定し、実現に向けて取り組むことが欠かせないのです。
SAWANNAを個包装のおしぼりに代替することで、具体的に削減できるプラスチックごみの量が算出できるため、認証取得の大きな一助となりえます。
水資源の節約につながる
SAWANNAから出てくる清潔なウェットティッシュは水道を使っての手洗いや水拭きのダスターの代替として活用ができます。そのため、顧客および従業員が使う水の量を減らすことができ、水資源の節約につながるのです。
水資源の節約はSDGsで掲げられる17の目標のうちの一つ「6.安全な水とトイレを世界中に」の目標に合致します。さらにグリーンキーおよびサクラクオリティグリーンの認証の項目の中にも定められており、認証取得の一要素として訴求が可能です。
SAWANNAの製品に関するお問い合わせ、認証取得に向けた導入のご相談はお気軽にご連絡ください。
まとめ
ホテルが取得を目指すべき認証「グリーンキー」と「サクラクオリティグリーン」について解説しました。認証の取得は現在社会的要請であるSDGsの取り組みとして高く評価されるだけでなく、ESG投資の対象となりやすい点や集客効果、従業員の就業意欲向上など、経営面でも様々な観点から有利になりうるものです。
現在行っているSDGsの取り組みを客観的に評価する指標としても有効に活用できます。ぜひ、自社にとってどちらの認証が好ましいのかを検討の上、認証取得に向けて準備を進めてみてください。
グリーンキー、サクラクオリティグリーンの認証取得の取り組みの一つとして、手をかざすだけでウェットティッシュが出てくるSAWANNAがおすすめです。複数の評価項目において加点要素となるため、導入方法や活用のご相談も含めてぜひお問い合わせください。